2023年08月01日(火)
葬儀の基礎知識 お葬式に仏式が多い理由
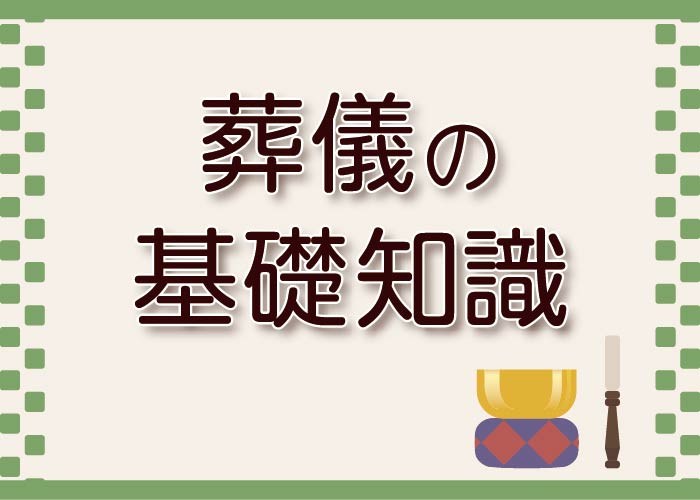
日本における仏式での葬儀の割合は
78~89%だと言われています。
なぜ、日本ではこれだけ仏式のお葬式が多いのでしょうか?
※この記事は個人的な見解をまとめたもので学術的な調査は行っておりません。
あらかじめご了承の上、お読みください。
《発端は江戸時代の寺請制度》
江戸時代にはキリスト教は禁教とされていました。
民衆の間にキリスト教が広まらないようにするために
江戸幕府は『寺請制度』を定めて、各地の寺院に対して
「この人はうちのお寺の檀家でキリスト教徒ではありませんよ」
という身分証のようなものを発行することを義務付けました。
つまり、江戸時代においては必ずどこかのお寺
(基本的には自分が生活している共同体の寺院)の
檀家であることが義務付けられることになりました。
この証明をしてもらわないと、士農工商の身分制度内に入れず、
つまりは正式な共同体の所属メンバーとして認められなかったそうです。
《宗門改め(しゅうもんあらため)》
また、宗門改めを定期的に行い信仰している宗派を調査し、
それを「宗門人別改帳」として報告させ管理していました。
《お寺は戸籍係の役割を持っていた》
「寺請制度」・「宗門人別改」の二つの制度をお寺が担っていたことにより、
各地の寺院は江戸時代における戸籍・住民票の管理を行う、
現代の役所の戸籍係の役割を持っていました。
(厳密には戸籍管理制度は寺檀制度がそれにあたるらしいですが役割的にほぼ同じものだと思います。)
戸籍を管理するということは、当然檀家さんの出生・死亡なども把握しており、
葬儀・法要などはお世話になっているお寺=菩提寺(檀那寺とも)で行うことになるので、
必然的に一部の特別な身分の方を除き、仏式での葬儀が一般化していったものと考えられます。
明治時代には廃仏毀釈の影響もあり寺請制度は廃止され、
戸籍等の管理も政府が行うようになりました。
また信教の自由が認められるようになり、必ずしも
「どこかの檀家に属していなくてはいけない」ということはなくなりましたが、
現代にも江戸時代の管理体制が影響して、仏式葬儀が多いのではないかと思います。
※記事内の用語の説明などは、厳密にはニュアンスが違うものもあるかと思います。
あくまで個人的な見解ですので、ご指摘をいただいた箇所は修正させていただきます。
